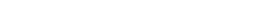- A
- 分かり易く言えばSEとは、お客さまの業務をシステム化するに当たり、お客さまとコンピューターの橋渡しを行うのが主たる仕事です。
SEには担当する仕事の範囲で上級SEから中級SE、初級SEに大別する事が出来ます。
お客さま側からシステム化する業務の内容と最終目的を聞き取り、業務の流れや仕組みを体系的に把握して文書化します。(これを業務フローと言います。)
把握して文書化された業務の流れや仕組みをシステム化するために、コンピューター的表現で文書化します。(やや専門的ですが、これをシステムフローと言います。) 基本的にここまでは上級SEの担当です。中級SEと初級SEは作成されたシステムフローに従いコンピューター言語を使ってプログラムを作成します。
その間、上級SEはお客さまと打ち合わせを行ったり、プログラムを作成している部下の仕事の進捗具合等を指導・監督します。
上級SEは、お客さまとのコミュニケーションや部下の指導・監督を行います。個人差はありますが、最低でも10年以上の経験は必要となります。
中級SEは7年前後の経験者、仕事の難易度により上級SEの代行が出来るレベルです。
初級SEは3年前後、一般的にはプログラマーと呼ばれる発展途上のSEの卵です。
採用情報
会社案内・採用に
関する情報
関する情報
よくある質問
会社説明会などを通じて弊社に寄せられる様々な質問の中から、代表的な質問をご紹介します。
- A
- 弊社では、入社後一年間は全員がコンピューターは素人を前提に独自のカリキュラムで研修を行います。企業は人材が命、「教育には時間と費用を惜しまず」が基本方針です。
まず入社後は、新入社員研修(情報処理基礎、合同技術集合研修など)を実施します。その後、各部署へ配属となります。各部の新入社員技術教育のカリキュラムに沿って教育担当者による基礎技術教育を受けます。 その後、職場の諸先輩からOJTでより実践的な技術教育を受けます。これで教育が終わるのではなく、その後も日常の実務の中で諸先輩の指導・支援を受け、更には定期・不定期な技術教育の受講等も用意されています。
殆どの新入社員は「コンピューターの知識・技術がゼロ」でのスタートですが、2年目には相応の仕事を、3年目ともなると立派に一人歩き出来るレベルまでに成長しています。また、弊社では派遣は一切しておらず、これがSE育成に大きな影響を与えています。何故なら、派遣先では重要な開発工程は殆ど担当させないからです。弊社はお客さまから仕事を一括受託するために、弊社のSEはシステムの提案、要件定義、基本設計、開発、テスト等々、上流から下流工程迄が経験出来ます。この事がSEの育成と成長に好影響を与えているのです。派遣中心ではなかなか経験出来ない事です。
- A
- 確かに、ハードウエアは電気や物理の知識・技術が必要ですから、文系では難しいと思います。しかし、ソフトウエア の場合は、我々は「文系の方にこそ適性がある!」と考えています。それは、SEに必要な能力は「システムの知識や技術以外に次の資質が重要」と考えるからです。
お客さまの考えを聞き出すコミュニケーション能力(会話力・表現力・説得力)が必要です。
アルバイト等から学び取った経験や幅広い人間関係は貴重な財産です。
意外にもSEの仕事には文章力・読解力や提案力が重要です。
折衝には一般教養や社会情勢、経済の知識等が必要になる事が多々あります。
お客さまのニーズを分析しニーズに合った的確な企画・提案を創りだす能力が必要です。
未経験分野でも積極的に挑戦する意欲的な姿勢が必要です。
もっとも、これはどの分野、或いは誰にでも必要な事ですが・・・。
何といっても弊社の70%強が文系出身者、まさに「論より証拠」です。
- A
- ソフトウエアの仕事は10人前後、大きくなればその倍以上のメンバーでプロジェクトを組み、お互いに協力しながら与えられた自己の担当範囲を処理します。上司は部下の力量と納期を考えて仕事を与えますが、進捗過程で思わぬトラブルが発生したり、本人のミス等で止む無く予定外の勤務時間が必要になる事は否めません。また、本人でなくチームのメンバーのミスで計画が狂う事もあります。納期が決まっている以上はチーム全体でカバーする事は当然、これが残業となってしまうのです。
さらに、お客さまの都合で仕事の内容が変更となっても、納期は変わらない・・・となれば臨機応変な対応が求められます。社員各自の残業をも計算に入れて多くの仕事を与える事は有りませんが、個人の能力差や本人のミスで残業が発生する人とそうではない人がいる事は仕方ないのかもしれません。
仕事の都合上、残業が発生する事はありますが、常識を超えるようなレベルではありません。特定の社員に負荷が掛からない様に仕事の分散を計って労務管理を行っています。
- A
- SEはコンピューター技術力だけではなく、お客さまのニーズを的確に把握・提案し、求められるニーズをコンピューターシステムへと具現化するのが仕事です。ところが、どの様に優秀なSEと言えども40歳を過ぎれば能力の低下は否めません。しかし、豊富な経験と習熟された技術力は大きな財産、この大切な財産を生かす事は本人は元より会社の発展に大きく影響します。
そのためには、先ず、本人の有する能力を的確に見抜き、更なる能力の指導育成を行わなくてはなりません。勿論、本人の努力なくして成長はありませんが・・・。
部下の指導・監督力、営業的センス、或いは豊富な経験と専門的技術・知識を生かす等の各専門分野における仕事こそ20年後のSEに求められる姿であると思います。即ち、「実務力発揮型技術職」であるシステム開発から「経験的知識・技術発揮型専門職」としての管理職、営業職、或いは高度技術専門職を目指す事がSEの将来像と思います。